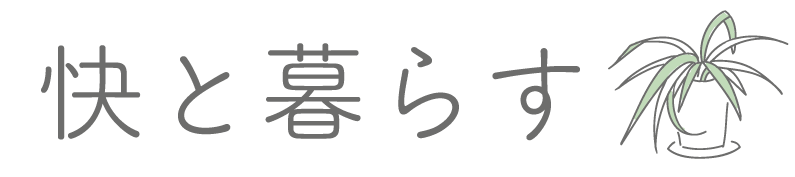欲しがるものは、わりかし買い与えてきた我が家。
先日、4才の娘に「おもちゃ買って!!」とごねられたのですが、
もしかして、わがままに育っちゃった?
物を大切にしなくなる?
なんて、子育てに迷走しました。
そんな時に、ネットの意見やリアルなママ友の意見を聞きまくったのですが
あ、そんな考え方もあるんだ!
という話もきけたので、意見をまとめつつ、我が家の方針や自論を述べていきたいなと思います。
 まどか
まどか買うとか、我慢をさせるという基準の他にも、「欲しいと思わせない環境作り」という視点は、納得でした。
おもちゃを欲しがる子どもに、買い与える派の意見
まずは、おもちゃを欲しがる子どもに買い与える派の意見を羅列してみます。
- 自分がおもちゃを買ってもらえなかったことで、大人になってから反動でモノを買いまくるようになってしまった。
- 「これは買ってもらってよかった」「これは、あんまりいらなかったかも」という、モノを選ぶ訓練になるから、とりあえず買ってもいいと思う。
- いつもは我慢させられるのに、「誕生日だから」と欲しいものを催促される時もあるのは、大人の都合で振り回しているだけな気がする。
- 本当に欲しいおもちゃを買ってあげた時、「自分で選んだ」という嬉しさがあったみたい。買ってあげてよかった。
これらの意見について、考察を述べていきたいと思います。
後から「いらなかったな」と思うような物でも与える価値はある
おもちゃを購入するためには、多かれ少なかれ親にとっては出費なわけでして。
これ3,000円するんやで?しっかり遊んでや?(´Д` )
と、ついつい「絶対大事にしろよな」みたいな圧をかけてしまうのですが。
でも、手に入れた物に対して、どれだけ大事にできるかどうかは、未知ですよね、大人でさえも。
そういえば、半年ほど前、Bluetoothのイヤホンを買ったのですが。
買ってから「なんか思ってたんと、ちゃう。」
ってがっかりして、ほったらかしにしていたという出来事がありました。
何度も買い物を重ねてきた大人(私)でさえ、「いらんもん買ってしまったわ。」って失敗があるんだもん。
子どもだって「買ってもらったけど、そんなに欲しいもんじゃんなかったな〜」って思うことはあるよね、あるある。
でもその失敗って「手に入れてからしか分からない」経験でもあるんだから、
本当に欲しい物を選ぶ訓練
の場を設けてあげることは、教育の一つなのかもしれませんよね。



自分のお小遣いの範囲内で痛手をこうむって欲しいところではありますけど。
「本当に欲しい」と感じたおもちゃなら、買ってあげたい
これが欲しい!このおもちゃが絶対ほしいわぁ!!!!
っていう物に出会えたら、親としてはもちろん買ってあげたいんです。
そりゃ、そうですよね。
でもね。
幼児ってそもそも「これが欲しい!」という物がなくても、
なにかおもちゃが欲しい!
って言い出すんですよね。
「え、なにかってなんなん?何が欲しいの?」
って聞いても
「欲しいものを探す!」とか言い出しちゃう。
いやいやいやいや、まってよ。
2時間ショッピングモールに滞在して、食料品も買い込んで、今から帰るところやで?
駐車場に向かって歩いているところですけど?w
と、こちらも思わず叫んじゃう。
子どもって、別に「欲しい!」って思えるものがなくても、
「なんか気分を変えたいな〜」みたいな時にだって「おもちゃが欲しい」って言い出すんですよね。
そして、そういう時ほど、よく泣くw
大人で言うと、
なんかリフレッシュしたいわ〜。スタバでも寄ってかん?
みたいな。
「そこに自販機あるけど?」なんて言われたとて、自販機ではリフレッシュできないわけです。
きっと娘も、
ガツっとおもちゃを手に入れて、ぱぁ〜っと気分をあげたいわ〜♡
みたいな感じなのかな、と思います。
そもそも、「これが絶対欲しい」と恋焦がれるようなおもちゃに出会えること自体、すんごい貴重なのかもしれませんよね。
そのタイミングだけは、逃さないようにしようと思います。



「これ欲しい!ダメ?じゃぁ、こっちは?」ってコロコロ欲しい物が変わる時も、多々あるw
おもちゃを欲しがる子どもに、我慢をさせる派の意見
次に、おもちゃを欲しがっていても、買わないという意見について羅列します、
- 幼少期におもちゃを買い与えすぎたのか、物に対して執着しない子になってしまった。
- おもちゃが家にありすぎて、1つ1つを大切にしてくれなくなった。
- おもちゃが多いと、片付けが大変になる。管理できない量を買うべきではない。
- 買わない理由をちゃんと説明すれば、分かってくれる。
- 家のルールだったり、「今日は買わない」って決めたのであれば、ごねられても曲げるのはよくない。子どもが混乱してしまう。
この意見からも、考察を述べようかなと思います。
「物に執着しない子」っていうのは、むしろ良いことなのでは
おもちゃはあんまり買わないほうがいい!という意見の中によくでてくるのが
「物に対して、興味をもたなくなる」
「物に執着しなくなる」
というフレーズだったのですが。
私としては、「物に執着しない」というのは、むしろプラスにも捉えられるのでは?と考えます。
物に対して関心が薄かったとしても、「人」や何かの「体験」に対して関心が高いのかもしれないし。
私自身、20才まで汚部屋に住んでて、少しずつ「物」への執着を手放しました。
そう言う視点でみると、子どもの時点で「物への執着」が少なめなのは、むしろ羨ましいな〜とも思います。
買わない理由を説明するのが、なかなか難しい
子どもにも理解力はあるので、買わない理由を説明する大切さもわかります。
ただ、買わない理由を説明するのが、なかなか難しかったりするんですよね。
「うちにはお金がないから買えない」っていうのは、絶対言わないようにしているけれど。
「今日は、そのおもちゃを買うお金は持ってきてないよ」も、今の時代はなかなか通じない。
カードか、スマホで買ってよ?
って言われた後の言葉に困ります。
「生活するためのお金も必要だから、おもちゃにはたくさん使えないよ〜」
って言いすぎると、「これが欲しい!」「あれがやりたい!」って言うのを遠慮するようになる気もするし。



うちは貧乏だから〜って言われて育った私は、欲しい物、やりたいことを言うのを何度もためらいました。子どもには、ひとまずストレートに欲求を言って欲しいです。
そんなこんなもあり、お金関連で幼児に説明するのは難しいな〜って感じています。
おもちゃを欲しがらない環境を作る派の意見
そもそも、おもちゃを欲しがらないように環境を整えればいい!
という意見が、ごもっともだったのでまとめます。
- 幼児が目の前におもちゃがある状態で、欲しがらない方が不思議。そもそもおもちゃがあるショッピングモールなどに出かけないのが正解。おもちゃ付きのお菓子を欲しがる時期であれば、買い物もネットスーパーで済ませばいい。時期的なものだから。
- 何か遊びたいものがあれば、家で一緒に作っています。
親の用事に付き合わせる頻度を下げよう
大人だって、服屋さんに行ったら服が欲しくなるし。
本屋さんに行ったら、本が欲しくなる。
同じように、子どもだってショッピングモールに行ったら、おもちゃが欲しくなって当たり前ですよね。
だから、
おもちゃが売っている場所に行かなければいい
うん、シンプルすぎる解決策。
今日は買ってあげられる日じゃないな〜って感じた時は、おもちゃが売っているところにはいかないようにしたり、
子どもが保育園や幼稚園に行っている間に買い物を済ませる!というのは、取り入れられそうです。



ただ、ここまで書いておいてなんですが。おもちゃ売り場で、もじもじ欲しそうにしている娘は可愛いんですよね。ぐずらなければ、欲しがってくれていいんですw←親の都合
4才娘に取り入れた我が家の方針
- お小遣いで買わせる。
- パパかママのお小遣いで買ってあげる。
- 買った分、何か手放すようにさせる。
- 本当に欲しい物であれば、買ってあげる。
- 欲しがる環境を、なるべく作らない。
- 欲求に対しては、共感する。
ここまで、ウダウダいろんな意見について考察してみましたが。
現時点の我が家の方針をまとめます。
①お小遣いで買わせる


お金関連で「買えないよ」「買わないよ」と説得するのは難しいな〜というのは先述しましたが。
買えない理由が
自分のお小遣いが足りない
というようであれば、本人も納得できるのかなと思います。
我が家では、3才から
- 何かお手伝いをして、誰かを助けた時
- 感動を与えた時
などに、不定期でお小遣いを与えています。
これは、家計の事情ではなく、本人の事情なので、一番本人が「買えない理由」が分かるかなと思います。
その上で、
買えるようにするには、どうしたらいいんだろう?
というのを、一緒に考えてあげられたらなと思います。
②パパかママのお小遣いで買ってあげる
4才児のお小遣いであれば、ガチャガチャなどは買えますが、さすがに数千円のものは買えません。
そんな時は、パパかママを納得させることができれば、買ってあげるようにしています。
娘の意見や様子をみて、
「買ってあげたいと思ったから、私のお小遣いで買ってあげるね」と。
それなら、
「今日は買ってあげる気持ちになれなかった」
と言っても、説得しきれなかった本人の責任でもありますしね。
「その金額は、買えそうにない」と伝えても、それはパパかママのお小遣いの範囲内の話であって、暮らしの生活がおびやかされるという不安を植え付けることもないかなと。



そんなに欲しいんなら、その気持ちをプレゼンして!交渉しよう♡と、よく言っています。6,000円のつみきを、パパとママと娘の3人で割り勘して買ったこともあります。
③買った分、何か手放すようにする
そもそも私がおもちゃを買いたくない理由というのが
家の中の物が増える
というのが、1番おおきい。
幼児が管理できるおもちゃの量って、たかがしれてますので、親がコントロールしてあげないと物が溢れかえります。
だからこそ、
おもちゃがたくさんあると、家が物だらけになって掃除がしにくいし、大事な物を失しやすくなるよ。1つ買うなら、使わないおもちゃを捨てるってお約束してね、
と伝えてあります。



私が作った段ボールの洗濯機とか買い物カートとかは、ガツっと捨てたいところ。でも手作りのものほど、大事にしてくれてるw
④本当に欲しい物であれば、買ってあげる
こちらも先述したとおり、
本当に恋焦がれるような物に出会えたら、買ってあげる
というのは、1つの方針にしたいところです。
ただ、その場で「欲しいっっっ!!!」って懇願してくるものと、長年大事にしているものっていうのは一致していないので。
買った後の娘の動向については、執着しない!と、自分の中で決めました。
ちなみに、一番大事に遊んでいるものは、1才の誕生日に姉夫婦に買ってもらった
ソランちゃん
です。
本人が欲しい!って言ったものではないのですが、かなり大事に使っているようです。
⑤欲しがる環境を、なるべく作らない
先述したとおり、
予定外の状況でおもちゃを欲しがるのは、欲しくなる環境を作っている親の責任
という意識は持つようにします。
⑥欲求に対しては、共感する
私は我が子に対して
欲しい!やりたい!行きたい!は訴えて欲しい
って思っています。
だからこそ、欲求を訴えてきてくれたときの対応には気をつけたいなと思っていて。
おもちゃが買える状況でも、買えない状況でも
欲しいと思った理由や、欲しいと思った気持ち
に対しては、共感した態度をとるようにしています。
「楽しそうだもんね、欲しくなるよね〜。」
「欲しい!って教えてくれたのは嬉しかったよ〜。」
などなど。
まぁ、こうやって言ったところで泣く時は泣くけどね。
「ダメなもんは、ダメ!」とか
「お金がないって言ってるでしょ?」
と言われるよりは、納得できるよね。
まとめ
ショッピングモールで
「なにか買ってよ〜〜〜!!!!」
とゴネられたのをきっかけに、今一度おもちゃの買う買わないの基準を模索してみましたが。
おもちゃを買うか買わないかという選択肢よりも
子どもが言いたいことを言える環境づくり
言ったことに耳を傾けてくれた!という満足感
を育めれば、一時的にギャーギャー泣かれようとも、よしとしようかなと思いました。



わがままを言いたい時期もあるしね、きっと。親が子どもの性格の全てを作り上げている!と責任を持つこと自体、傲慢なのかもね。
\「甘え」と「甘やかし」の違いが分かりやすかった本/